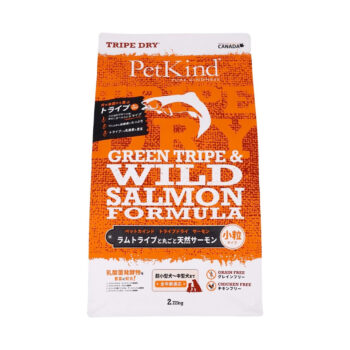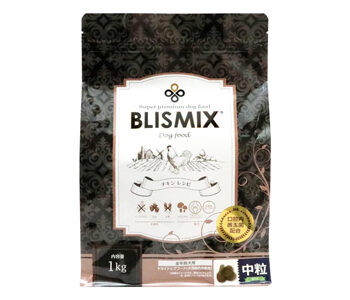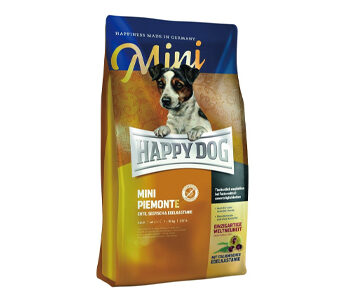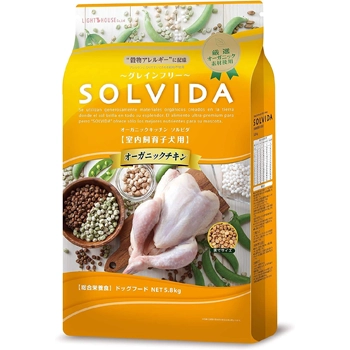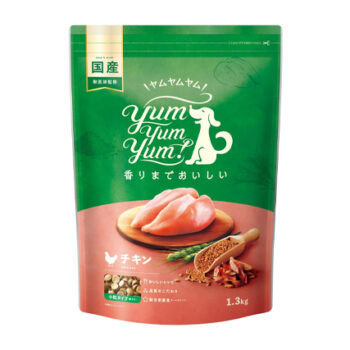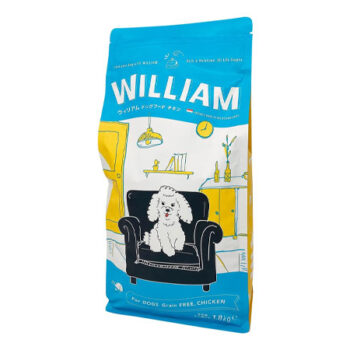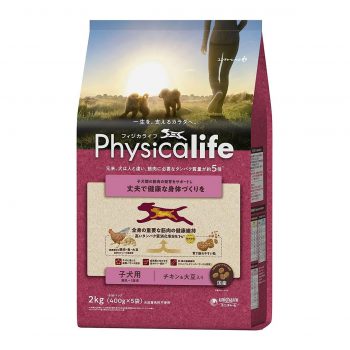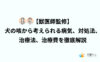愛犬の便を片付けるときに毎回便の状態をチェックしていますか?
私たち人間と違って言葉で自分の健康状態を訴えることができない犬にとって便は健康状態を教えてくれる大切なサインの1つとなります。よって可能ならば片付けてしまう前に便の硬さや色、形、臭いなどをじっくり観察するようにしましょう。
また、愛犬が下痢や軟便をしているときは単なる一時的な不調と考えて様子を見るのではなく、健康状態に何かしらのトラブルが発生している可能性があると捉えることが健康を守るポイントともなります。
よって今回は、犬が下痢や軟便をした時の原因や対処法などについて解説していきたいと思います。
犬の正常便と下痢、軟便との見分け方
正常な便とはどのような状態?
個体差や年齢による違いはありますが、犬の正常な便とは一般的に以下のような状態が該当します。
| 硬さ | 指で押すと、少しへこむくらい。 またコロッとしておりビニール袋越しに拾っても崩れたりせず地面や床にも付着しない。 |
| 色 | 主食にしているドックフードにもよりますが、多くの場合は濃い目の黄土色や焦げ茶色。 |
| 形 | ソーセージやバナナのような円柱状 。 |
| 臭い | 多少の便独特の臭いはあるが、換気を必要としない程度。 |
犬の下痢や軟便とはどのような便?
こちらも正常な便と同じように、個体差や年齢による違いはありますが以下のような便が見られたらあまり状態が良くない便となります。
形はあるが、いつもより柔らかい便
正常な便と同じように円柱状を保っていますが指で押すと簡単につぶれてしまう、コロッとはしていない、片付けた際に地面や床に少し便が残ってしまう、拾うと簡単に崩れてしまう、などの場合は「軟便」の可能性が高い状態です。
形がなく、液体に近い便
形がなく泥のようである、地面や床にもべったりくっついていて簡単に便だけを取り除くことができない、などの場合は「下痢」の可能性が高い状態です。
また、正常な便と比べて悪臭がしている、犬がお尻についた下痢便を取るために床にお尻をこすりつけることによって、便が周囲の床になどにたれているなどの特徴が見られることもあります。
便に血が混じっている場合は?
血が混じっている場合における便の色の異常としては「黒色便」と「鮮血便」が、よく見られます。
「黒色便」は便が真っ黒い色をしており、別名「メレナ」や、「タール便」と呼ばれることもあり、主に口腔内や食道、胃、十二指腸、小腸などからの出血が疑われます。「鮮血便」は便に赤い血が混ざっており、主に大腸や肛門などからの出血が疑われます。
犬の下痢や軟便の分類
一般的に下痢や軟便は便に含まれる水分量が正常時より増えることによって起こり、多くの場合は腸に何かしらのトラブルが発生しています。腸は「小腸」と「大腸」に大きく分けることができ、下痢のタイプによってどちらに問題が起きているか鑑別することができる場合もあります。
小腸にトラブルが起きている「小腸性下痢」
小腸に何かしらの異常があって起こる「小腸性下痢」の場合は、正常時と比べて排便の回数はあまり変わりませんが、一回あたりの便の量が増えるという特徴があります。また、小腸に出血が起きている場合は「黒色便」が見られることもあるでしょう。
大腸にトラブルが起きている「大腸性下痢」
大腸に何かしらの異常があって起こる「大腸性下痢」の場合は、正常時と比べて排便の回数は増えて、かつ一回あたりの便の量は少なくなるという特徴があります。また、大腸に出血が起きている場合は「鮮血便」が見られることもあるでしょう。
このように下痢をする回数は少ないけど1回あたりの便の量が多い場合は「小腸性」、こまめに下痢をするけど1回あたりの便の量は少ない場合は「大腸性」の可能性が高いことから、動物病院での問診の際に、これらの情報を伝えることが下痢の原因を見つけることに役に立つときもあります。
犬の下痢や軟便の原因
犬が下痢や軟便をする原因には様々なものが考えられるため、その症状だけで特定することは困難です。ただ、中には病気が原因ではない一時的な反応の場合もあるため、犬に下痢を引きおこす要因について飼い主さんは理解しておくことを、ぜひおすすめします。
病気によるもの
動物病院では便を顕微鏡で観察する「検便」を行うことがほとんどのため、愛犬が下痢や軟便をして通院する際には便をビニール袋などに入れて持参するようにしましょう。
場合によっては血液検査、レントゲン検査、超音波検査などのより精密な検査が必要になることもあります。
病気によるものの一例として、検便によって寄生虫が見つかった場合は寄生虫感染による可能性が高いため、まずは駆虫薬の投与による治療が第一選択肢として行われますし、特定のフードを与えたときにのみ下痢や軟便が見られるならば食物アレルギーが疑われます。
ストレスによるもの
引っ越しや来客などをストレスと感じて、下痢や軟便をしてしまう場合もあります。愛犬が繊細なタイプの場合は、可能な限りこれらのストレスとなりそうな行動は控えてあげたほうが良いでしょう。
冷えによるもの
私たち人間よりも、かなり低い位置にいることが犬は多いため室温と犬が感じている体感温度には差があると考える必要があります。基本的に「冷たい空気は下へ下がり、暖かい空気は上へ上がる」という性質があるため、夏は冷房の冷たい空気が、冬は床からの冷気が犬に当たることが多く、その「冷え」によって下痢や軟便を起こしてしまう場合があります。
可能ならば犬がよくいる場所の、かつ犬の目線に近い位置に温度計を設置してあげて、温度管理を適切に行なってあげるようにしましょう。
急なフードの切り替えによるもの
子供や消化器官が敏感な方などが普段食べ慣れてないものを食べた場合にお腹を壊してしまうことがあるように、犬においても食事が原因で下痢や軟便をしてしまうこともあります。
特によくあるのが、新しいフードに替える必要があった際に、急に切り替えてしまうことで消化機能が上手く働かず、その結果として下痢や軟便が引き起こされてしまうというパターンです。
獣医師から指示があった時は別ですが、フードを替える際は急に切り替えるのではなく最初の数日間は新しいフードを四分の一と残りは以前のフードを混ぜて与えてみて、問題なさそうならば次の数日間は新しいフードと以前のフードを半分ずつ、のように少しずつ切り替えることがおすすめです。
愛犬が下痢、軟便をした時の対処法
愛犬が急に下痢や軟便をした場合は、パニックになってしまう飼い主さんも多いと思います。
可能ならば、かかりつけの動物病院を受診するか、または電話などで相談することがベストですが飼い主さんの状況、時間帯などによってはこれらの対応を取ることが難しい場合もあるでしょう。
よって、最後に犬が下痢や軟便をした時の対処法について解説していきます。ただ、あくまでも参考程度に留めておいて、必要と感じたならばすぐに動物病院に相談してくださいね。
下痢や軟便以外に症状がない場合
愛犬が下痢や軟便をしてしまった以外は食欲や元気もあり、また嘔吐などの他の症状がない場合は直近でストレスとなる行動をしなかったか、新しいフードを与えなかったか、室温は適切かなど病気以外の原因を考えてみましょう。
もし、思い当たる原因があるならばそれらを取り除くか改善してみて、下痢や軟便が一時的なものであったとすると、繰り返さないようにこれからの行動に気をつけてあげる必要があります。
思い当たる原因がない、またはそれらを取り除くか改善してみても下痢や軟便が続く場合は早めに動物病院を受診することをおすすめします。
下痢や軟便以外に症状がある場合
下痢、軟便以外にも食欲不振や元気消失、嘔吐などの他の症状がある場合は病気による可能性が高いため、早々に動物病院を受診するようにしましょう。その際は、下痢便を持参することを忘れないようにしてくださいね。
子犬や老犬、持病がある犬の場合
下痢や軟便をしているということは、「必要な水分や栄養素が便として体内から出てしまっている」とも考えることができます。よって子犬や老犬の場合は脱水症状などになりやすい可能性が高いため、下痢以外に症状がなくても可能な限り早めに動物病院を受診してあげましょう。
また、何かしらの持病にて治療中の場合も状態が悪化してしまう危険性があるため、動物病院に相談するようにしてあげてください。
ドッグフードの見直しが必要な場合も
獣医師の指導が必要となりますが、消化器官が敏感な犬用の療法食を与えることで下痢や軟便が改善することもあります。消化器をサポートする療法食の多くは消化性が高い原材料を使用しており、また健康的な腸内細菌バランスに配慮してサイリウム、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖などの可溶性食物繊維を配合していることが特徴となります。
食物アレルギーによって下痢や軟便が引き起こされている場合は、アレルゲンとなる原材料が含まれていないフードに切り替える必要があるでしょう。
まとめ
大切な家族の一員である愛犬が下痢や軟便をしているかどうかを気づくことができるのは、飼い主さんだけです。健康トラブルに早く気づくためにも便を片付ける際には状態をチェックするようにしましょう。
犬が下痢や軟便をする原因には様々なものが考えられますが、他の症状がない場合はストレスやフードの急な切り替えなどの病気以外の理由がないかまずは考えてみることも大切です。
ただ、子犬や老犬などの体力が無い状態や嘔吐、食欲低下などの症状が見られる際には可能な限り早めに動物病院を受診するようにしてあげてくださいね。

 ドッグフードの評価一覧
ドッグフードの評価一覧