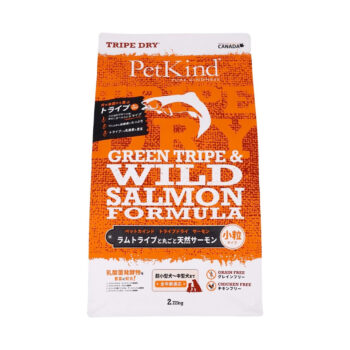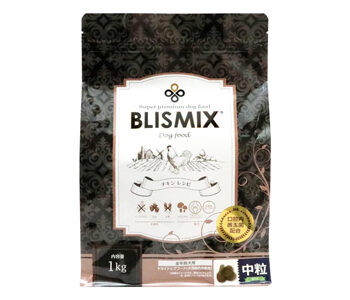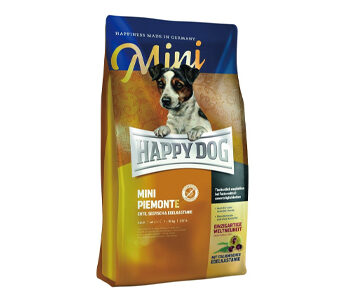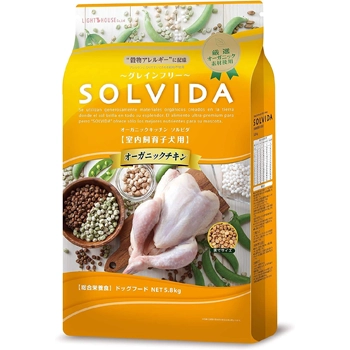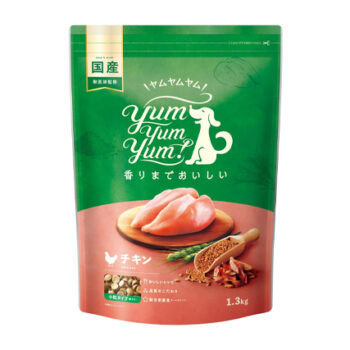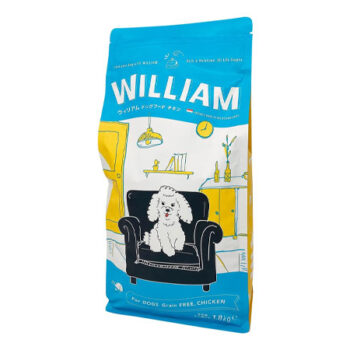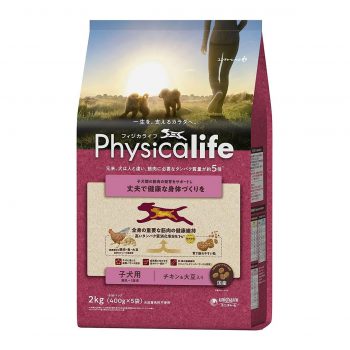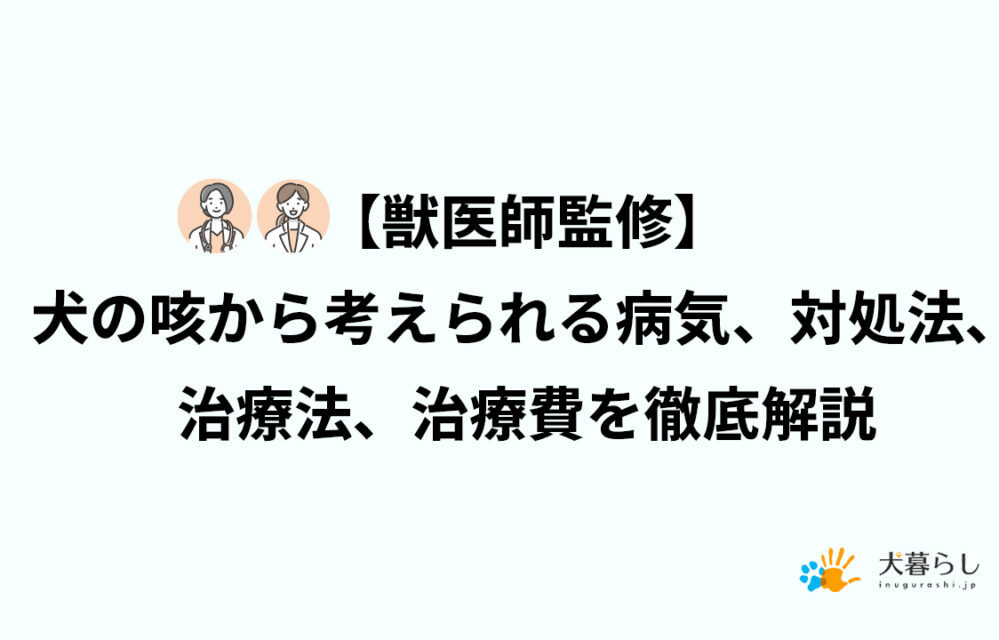
愛犬が「カハッ」「ガッ」などといった音を出した場合、それは咳の可能性があります。犬も私たち人間と同じように咳をしますが、聞こえてくる音や仕草などが人の咳とは異なるため、なかなか咳とは気づかない飼い主さんも多いようです。今回は犬の咳から考えられる病気や治療法などを解説しますため、ぜひ参考にしてくださいね。
咳の症状とは
そもそも「咳」とは、鼻から肺までの空気の通り道である「気道」に侵入したほこりやウイルスなどの異物を排除するための防御反応の1つとなりますが、それ以外にも何かしらの原因により気道に炎症が生じた場合などにも起こる症状です。
犬が咳をする場合は、「カハッ」「ガッ」などといった音を出すとともに呼吸がしにくそうな様子が見られます。
似たような様子が見られる症状として「嘔吐」があります。
嘔吐の場合は消化途中のフードや胃液などを吐き出すことがほとんどとなります。
ただ、たまに吐きたそうにするのに何も吐かない「空嘔(からえずき)」が起こることもあり、飼い主さんだけでは咳か嘔吐なのか判断できないケースもあるため、そのようなときは愛犬の様子を動画にて撮影した上で、受診するようにしましょう。
考えられる代表的な病気と治療費
犬が咳をする原因としては病気の症状によるものと生理的現象によるものと大きく2つに分けることができますが、ここからは咳が見られる代表的な4種類の病気とその治療法、治療費について解説していきます。
ただ、治療費や治療期間はあくまで一例となり、症状の程度や治癒するまでの期間、動物病院によっても大きく変動しますので、参考程度にとどめておくようにしてくださいね。
また、『実例で知る犬の医療費・治療費とは?』では動物病院にかかった方の治療費アンケートが記載されていますので、ぜひご確認ください。
ケンネルコフ
ケンネルコフは正式な病名として「犬伝染性気管気管支炎」といい、主にウイルスや細菌の混合感染が原因で発症する呼吸器疾患です。
ケンネルコフの症状とは?
症状としては咳以外にも発熱や鼻水、食欲不振、元気消失といった風邪のようなものが見られ、多くの場合は免疫力の低い生後6カ月未満の子犬や老犬に発症します。
ケンネルコフの治療内容とは?
軽症の場合は抗生剤や咳止めの内服に加えて吸入器を使用して霧状にした薬を吸入させるネブライザー治療を行うことが主となります。また、場合によっては自己免疫力を高めることを期待してインターフェロンの注射を行うこともあります。
重症化して肺炎などを引き起こしてしまった場合は、入院が必要となることもあるため早期発見と早期治療が大切です。
ケンネルコフの治療費用の例
実際にケンネルコフと診断されて通院のみで治癒した場合に想定される治療内容と治療費用
| 治療期間 | 2週間(1週間に1回の頻度で通院) |
| 通院回数 | 2回 |
| 治療内容 |
|
| 治療費 | 20,000〜30,000円程度 |
実際に当サイトのアンケートで拝見した領収書は28,000円程度でした。
以下がその実例です。
| 症状と内容 | ケンネルコフ(疑い) |
| エリア(病院名) | 福岡県(室○動物病院) |
| 治療費 | 28,000円程度 |
当サイトコラム『実例で知る犬の医療費・治療費とは?』から引用しております。
犬フィラリア症
寄生虫の一種である犬糸状虫による感染症です。
犬フィラリア症の症状とは?
寄生虫の一種である犬糸状虫の成虫が主に肺動脈や心臓の右側に寄生することで血液循環障害を起こし、咳や散歩などの運動を嫌がる運動不耐性、肺水腫などの症状が見られます。適切なスケジュールにてフィラリア幼虫の駆除薬を与えたり皮膚に滴下したりすることでほぼ100%の確率で防ぐことができるため、飼い主さんの義務としてフィラリア症予防は必ず行うようにしてください。
犬フィラリア症の治療内容とは?
外科手術と内科治療があります。
外科手術は肺動脈に寄生している成虫を取り除く方法です。この外科手術は難易度が高く、麻酔のリスクがとても大きいため、重度のフィラリア症でなければ選択されることはあまりありません。また、重度の場合は犬の体力が落ちていることも考えられるためかなり慎重な判断が必要となります。
内科治療はフィラリア駆虫薬の投薬を行います。
おおよそ5~6年間と考えられています。また、定期的に画像検査などで成虫の状態を確認する必要があります。
犬フィラリア症の治療費用の例
ここでは内科治療の場合の治療費用を紹介します。
使用する薬や種類の検査内容などによって異なりますが、フィラリア症の検査結果が陰性となるまでは約20~30万ほど必要となることもあるでしょう。
治療費用の想定としては以下です。
| 治療期間 | 6年間(1ヵ月に1回の頻度で通院) |
| 通院回数 | 72回 |
| 治療内容 |
|
| 治療費 | フィラリア症予防薬代2,000円程度(毎月) / 不定期で検査代10,000円程度 |
実際に当サイトのアンケートで拝見した領収書は月1,200円、エコー検査2,000円程度でした。
とても良心価格の病院のようです。
| 症状と内容 | フィラリア症治療 |
| エリア(病院名) | 福岡県大野城市(○ンバ○ー動物病院) |
| 治療費 | 月1,200円程度(ミルベマイシン処方) エコー検査2,000円(不定期) |
当サイトコラム『実例で知る犬の医療費・治療費とは?』から引用しております。
気管虚脱
気管は鼻や口と肺を繋ぐ空気の通り道であり、ホースのような形となっています。そのホースのような形が何らかの原因で押しつぶされたように変形してしまい、空気の通り道が狭くなってしまう病気を期間虚脱といいます。原因は現時点では解明されていませんが、遺伝による影響や肥満、首輪を引っ張るなどの物理的な気管の圧迫も影響しているのではないかと考えられています。
気管虚脱の症状とは?
症状としては咳や「ガーガー」というアヒルの鳴き声のような異常な呼吸音が見られるため、そのような場合は可能ならば動画を撮影した上で動物病院を受診するようにしましょう。
気管虚脱の治療内容とは?
軽度であれば咳止めや気管支拡張薬などの内科治療によって治癒ではなく症状のコントロールが行われますが、重度になると気管の形を維持するための外科手術を必要とする場合もあります。原因が解明されていないため明確な予防法は無いのですが、肥満にさせないことや首輪ではなくハーネスを使用するなどといった喉への刺激を可能な限り避ける対策をとるようにしましょう。
気管虚脱の治療費用とは?
内科治療のみでコントロールを行う場合はおおよそ1ヵ月で3,000円~5,000円以内の範囲で収まることが多いですが、外科手術を行う場合は入院と手術を含めて総額で数十万円ほどの費用を必要とすることもあるため、今後の治療方針についてはかかりつけの獣医師とよく相談するようにしましょう。
以下は実際に犬気管虚脱と診断されて内科治療のみでコントロールする場合に想定される治療内容と治療費用は以下です。
| 治療期間 | 生涯 |
| 通院回数 | 1ヵ月に1回の頻度で通院 |
| 治療内容 |
|
| 治療費 | 1ヵ月分のお薬(気管支拡張薬など) 代3,000円 (毎月) / 不定期で検査代5,000円 |
僧帽弁閉鎖不全症
心臓は左心房、左心室、右心房、右心室と4つの部屋に分かれており、全身に送られた血液は静脈を通って右心房に戻され、右心房⇒右心室⇒肺⇒左心房⇒左心室⇒動脈を通して再び全身へ送られています。この流れにて逆流が起こらないように左心房と左心室の間に「僧帽弁」、右心房と右心室の間に「三尖弁」というドアのようなものがありますが、そのうちの「僧帽弁」が変性して左心室⇒左心房へ血液が一部逆流してしまう病気を僧帽弁閉鎖不全症といいます。原因は老化による僧帽弁の変形や、歯周病菌が僧帽弁に付着することによって菌が増殖し弁に塊を作ってしまい弁の働きを阻害することなどが考えられています。
僧帽弁閉鎖不全症の症状とは?
症状としては頻繁な咳や疲れやすくて散歩の途中に座り込んでしまう運動不耐性、心雑音などが挙げられます。
僧帽弁閉鎖不全症の治療内容とは?
軽度であれば血管拡張薬や利尿剤、強心薬などの投薬治療によるコントロールが行われますが、根治を望むならば専門的な心臓外科手術となります。予防法としては心臓への負担を減らすために適性体重を保つことや歯周病菌を減らすための日常的な歯磨きなどのお口のケア、早期発見のための定期的な健康診断が挙げられます。
僧帽弁閉鎖不全症の治療費用とは?
内科治療のみでコントロールを行う場合はおおよそ1ヵ月で3,000円~10,000円以内の範囲で収まることが多いですが、外科手術を行う場合は入院と手術を含めて総額で100万円~200万円ほどの費用が必要となるといわれています。また、手術が可能な病院も限られてくるため、今後の治療方針についてはかかりつけの獣医師とよく相談するようにしましょう。実際に僧帽弁閉鎖不全症と診断されて内科治療のみでコントロールする場合に想定される治療内容と治療費用は以下です。
| 治療期間 | 生涯 |
| 通院回数 | 1ヵ月に1回の頻度で通院 |
| 治療内容 |
|
| 治療費 | 1ヵ月分のお薬(血管拡張薬など) 代3,000円 (毎月) / 不定期で検査代10,000円 |
犬が咳で苦しい時にできること
愛犬が咳をしているからといって必ずしも病気によるものであるとは限りません。私たち人間と同じように空気が乾燥していても咳が出る場合があるため、湿度計を用いてお部屋の湿度を適切に保ってあげるようにしましょう。また、首への負担を避けるためにも、引っ張る癖がある犬の場合は特に首輪ではなくハーネスに交換することをおすすめします。
さらに適切な量のフードを与えることや愛犬の種類に沿った運動量を確保することで肥満を防いだり、歯磨きを毎日行うことで口腔内の環境を清潔に保ったりすることなどで、愛犬の健康を守ることは咳の予防策にもつながります。
まとめ
犬の咳は私たち人間とは仕草が異なるため、なかなか咳をしていると気づくことができないかもしれません。よって愛犬がいつもとは違う音を出した場合は、動画を撮影しておくことをおすすめします。また、咳の原因は病気によるものとは限りませんが様子見をしていると重症化してしまう危険性があることから、こまめに愛犬の様子をよく観察するようにしてあげてくださいね。

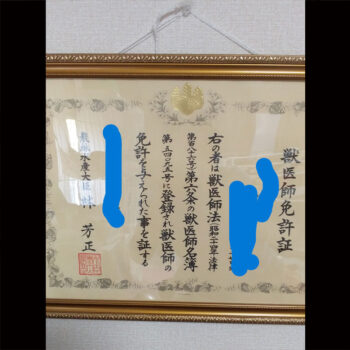



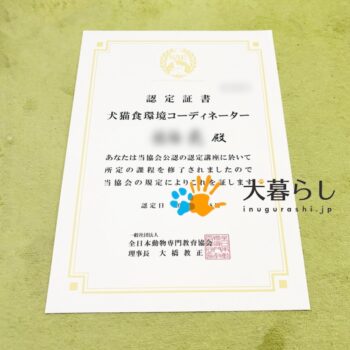

 ドッグフードの評価一覧
ドッグフードの評価一覧